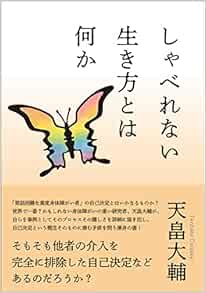
このように見ていくと、それと対照的な方向であると気づくのだが、もう一つ、自分が作ったと言いたい思いが(すくなくとも一方では)あることがある。そしてそれも言われればもっともな思いではある。天畠大輔がそういう思いの人である〔文献略〕。彼は、世界で一番?、かもしれない身体障害の重い大学院生で、発話できず、身体の細かな動きはできないので、通訳者が「あかさたな」と唱えるのを聞いて身体を揺するのを通訳者が読み取り、次にあ行なら「あいうえお」と唱え、「う」で確定といった具合に話す。想像するよりはずっと早く進むが、しかし時間はかかる。視覚障害もある。長い文章、とくに博士論文といった長く面倒な文章を書こうとなると、どうするか。
彼には長い時間をかけて育ってきたきわめて優秀な通訳者が複数いる。普通の意味での通訳にも熟達しているが、長年付き合ってきて、何を天畠が考えているかもわかっているし、この通訳という仕事がどんなものであるかもよくわかっている。だから、このコミュニケーションを主題に書かれるその博士論文について、本人の意を察するという以上のことができることがある。それで天畠はかなり助かっていて、それがないよりはるかに楽ができていると思うとともに、そして依存する気持ちのよさを味わうとともに、自分の仕事が自分の仕事として認められたいと思う。そういうジレンマを抱えているのだと書く。
それをジレンマと言えるのかどうか。自分でやっていると言いたいが、手伝ってもらってもいる。そしてそれはそれで心地よく、楽でもある。他方、彼自身が寄与しているのも間違いない。そもそものアイディアを出すということもあるし、そのチームを作ったのも、彼、彼の身体である。どれだけと確定はできないが、彼は寄与している。同時に手伝ってもらってよくなっている。それだけのことである。だから共著ということにしたいのであれば、すればよい。論文も学会報告も、ほとんどすべてがそのようにして発表可能である。
ただ学位は個人に対して与えられる。個人を評価したその結果が学位であって、その成果には、もちろん環境があり、人との関係があったうえであること等々を承知しつつ、一人に一つ出すというものである。その合理性はあるか。例えば職を得る/与えるための指標であるとしたらどうか。普通は、人は一人採用するということになるから、その際の指標は、一人について一つということになりそうだ。このように一人につき一つが必要とされる場合があり、そのように求められることにつきあってもよいという人はその世界の流儀に従うことになる。これ以上つついても仕方がない。他方、同時に、仕事は共同で行なったといって何も問題はない。」